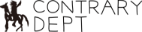Dissertation
Tango Chirimen and Te-Nassen / 丹後縮緬と手捺染
日常生活から着物や風呂敷が失われゆくにつれ、縮緬もまた徐々にその姿を消しつつあるが、その技法は世界でも類を見ない、日本独自のユニークなものだ。長い歴史の中で培われてきた技術を現代に活かすよう、新たな素材や技法の開発を含め、さまざまな道が模索されている。
| Category: | Material |
|---|
| Date: | 2022.07.27 |
|---|
| Tags: | #tangochirimen #tenassen #visvim #丹後縮緬 #手捺染 |
|---|

製織と染色、失われゆく技の掛け合わせが生む新たなプロダクト。
「丹後縮緬」は京都府北部、日本海に面した丹後地方で約300年前から織られてきた織物。「縮緬(ちりめん)」とは、経(タテ)糸に無撚糸(撚りのかかってない糸)を、緯(ヨコ)糸に強撚糸(撚り数の多い糸)を用いて織ることで、精練の際に撚りのかかった糸に撚りを戻そうとする力が働き、布の表面に微小なシボ(皺)が表れるもので、素材には強撚に適した特性から長繊維である生糸が使われる。絹織物の凹凸が醸し出す奥行きある表情、しなやかな手触り、皺になりにくく伸縮性が高いことを特長とし、古来より高級着物の素材として重宝されてきた。
丹後は約1300年の昔より絹織物の産地であったが、享保5年(1720年)に峰山町に住む絹屋佐平治(後に森田治郎兵衛と改名)が京都西陣の機屋に奉公人として入り、縮緬の技法を研究して丹後に持ち帰り、その礎を築いたとされる。技術が普及した丹後地方一体で生産されるようになり、江戸後期〜昭和初期にかけて「丹後縮緬」として隆盛をきわめた。


京都府与謝郡与謝野町には、かつての縮緬商家を含めた町の賑わいを伝える「ちりめん街道」と呼ばれる町並みが保存されている。古の時代より機織りの音が響き渡ったこの地で現在も縮緬を生産する「山藤織物」は天保4年(1833年)創業。6代目の山添憲一さんの案内により訪れた同社の工場には、縮緬に欠かせない強撚糸を生み出す「八丁撚糸機」が並んでいた。動力を使い同時に複数の糸を撚るこの機械は江戸期に発明され、主に明治の中頃まで生産の主力として広く使用されたもの。山藤織物ではその八丁撚糸機が今も現役で稼働している。



丹後縮緬の生産は、生糸を目的の太さにする「合糸」、糸を釜で炊いて柔らかくする「緯炊き」、撚糸機にかけるための管に巻く「下管巻き」、八丁撚糸機による「撚糸」、そして強撚をかけた糸を他の糸と合わせて生地を織るという過程を経る。合糸の本数は一般的に3〜30 本程度で、厚めの着物地で16本前後とされている。
八丁撚糸機に生糸を巻いた下管をセットして、木製の車輪(元車)を回転させると、ロープを伝った動力によりコマが回転し、糸に撚りがかけられていく。その際、「静輪(しずわ)」という磁器製の重りをつけ、均一に撚りがかかるようにテンションをかける。撚りの数は、静輪の重さ、コマの回転数、送り出される糸の量で変化し、1メートルにつき1,500〜4,000回ほどの撚りがかけられる。糸の太さを含め、それら複雑な要素すべてを適切に調整することで、生地のコシ、手触り、風合いを絶妙にコントロールするのはもちろん職人の高い経験値と技術である。

強く撚りを掛けると繊維が切れやすくなるため、糸には常に水をかけて湿らせておく。太い糸であれば撚糸に数十時間もかかるが、その間、職人は糸が切れていないかを常に確認し、調整・修復しなければならない。撚糸を巻取る糸巻きには昔から、桜の木を5年以上寝かせ乾燥させたものが使われてきた。巻き付いた生糸が乾燥すると強く収縮して木に食い込むため、硬い金属製だと糸が切れてしまうので代用できないという。
織る際には、経糸に右撚り2本と左撚り2本の緯糸を交互に織り込むが、これを1本または3本を交互に入れることで、シボに変化をつけることができる。左右の撚糸を一越(緯糸1本)ごと交互に織り込んだ一越(ひとこし)縮緬は特にシボが細かく、手触りも柔らかい。その他、さまざまな表情を持つバリエーション豊かな縮緬が生み出されてきた。

昭和初期頃までは着物、戦後は風呂敷などの高い需要があり、「織れば売れる」と言われたほど全国に広く普及していた丹後縮緬だが、高度経済成長期後には生活スタイルの変化により需要が減少。1970年代半ば頃には約990万反もあった着物地の年間生産量は、現在は約17万反にまで落ち込んでいる。
日常生活から着物や風呂敷が失われゆくにつれ、縮緬もまた徐々にその姿を消しつつあるが、その技法は世界でも類を見ない、日本独自のユニークなものだ。長い歴史の中で培われてきた技術を現代に活かすよう、新たな素材や技法の開発を含め、さまざまな道が模索されている。製法上、水に濡れると縮みやすく風合いも失われてしまうという縮緬の弱点を克服した「防縮加工」もそのひとつ。〈visvim〉のシャツにも施されており、ウォッシャブルな製品として仕上げられている。

織り上げられた〈visvim〉の丹後縮緬のシャツ生地に、1版ずつ職人の手で染め上げる「手捺染」を施すのは、大正2年(1913年)創業、京都市伏見区にある「馬場(ばんば)染工場」だ。大正期から使用する合掌造りの工房には、全長約27メートルに及ぶ傾斜した加工台が設置されている。この加工台に染色にも使用する布糊を薄く引いた上で、風呂敷などで使われる二四巾(二尺四寸)の反物生地を長さ約25メートル分、皺にならないよう手際よく広げて貼り付けていく。これだけでも長い経験が必要な、慎重を要する作業だ。



台に貼った生地の上に版をセットした後、糊貯めの道具をセットして、色糊を流し込み、シルクスクリーンの要領で一色一枚ずつ上からヘラで素早く刷っていく。途中でヘラの動きを止めると色ムラが出やすいため、一反25m分を一人で一気に染め上げるのだという。色数によって型紙の数が決まり、今回の〈visvim〉のシャツは柄だけで3版、地の色に2版の計5回、一枚の布に一色ずつ重ね合わせて染めている。




特に難しいのは、指定の色に調合する「色合わせ」の作業。色見本を見ながら、元糊、染料、助剤などを混ぜ合わせて調合する。生地がすべて同じ色味になるよう、グラム単位で微細な調整を行っていく。素材の特性はもちろん、気温や湿度によっても色が微妙に変化するため、経験に裏付けられた繊細な感覚が必要とされる。シルク(絹織物)である丹後縮緬の場合は、糠糊(ぬかのり)も使うことがある。米糠糊に塩などを入れて一年ほど前から寝かせておいたものだ。

布の乾燥を早めるよう、加工台の金属板の下にはスチームの熱源が仕込まれているため、工房内の室温は夏には蒸し風呂のような暑さになるという。過酷な作業だが、「生地、染料、道具が違えば、染まり方もすべて変わってくるのが面白い」と話すのは、若き職人の児島怜さん。学生時代に授業で工房を見学に訪れ、その染の技法に魅せられて入社したという。現在は四代目の馬場憲生さん、先代の善久さんとともに工房を支えている。




生地をすべて捺染し乾燥を終えたら一度巻き取り、蒸し、水洗い、湯のしの工程を経て完成する。蒸す温度や洗いの方法にも生地の素材ごとに加減が必要となる。「シルクは染まり易い、だからこそ難しい」と憲生さん。「綿なら高温の水で染まるが、絹は低温でも染まる。それゆえに、洗う際の温度を間違えると、色が他の部分に写り汚れてしまうんです。しかもシルクは生地によって個体差も大きい。やっぱり動物素材、生き物ですからね」。最後に頼りになるのは、職人による長年の"勘"だ。日々の地道な作業、そして経験が育む豊富な知識と精密な技術、そのすべてが合わさって、ひとつのプロダクトが生まれてくる。
文: 井出幸亮
写真、動画: 深水敬介
動画編集: cubism